どうもです、タドスケです。
最近、社内でプログラミング経験ゼロのデザイナーさんが、生成 AI を使ってカジュアルゲームを一日一本作るというチャレンジをしている話を聞きました。
一日ごとにメキメキクオリティが上がっていて、AI の提案のままに今では GitHub まで使いこなしているそうです。
とても素晴らしいと思うと同時に、

これからこういう人たちがどんどん出てくるんだろうなぁ…
という危機感も覚えました。
ただプログラミングが得意なだけでは、エンジニアとしての価値は出せない時代になってきています。


こちらの記事を書いたのが4年前。
生成 AI も出てきたいま、改めて自分なりの生存戦略をまとめてみました。
AI に任せるついでに AI から学び、倍速で成長する
AI の回答のクオリティは日に日に上がってきていますが、回答が正しいかどうかを判断し、利用にあたって責任を取るのはあくまで人間です。
そのためには、AI を使う側の人間も学び続けなければいけません。
かといって「自分でやらなきゃ成長しない」という考えも、この時代には少し古いように思えます。
新しい技術をじっくり学んでいる間に、もうその技術は廃れてしまうかもしれない。そんな時代です。
初めから AI を積極的に使いつつ、「なぜそうなるのか?」を AI に分かりやすく解説してもらい、自分も倍速で成長する。
それくらいの感覚が良いのではないかと思います。
メンバーの頭の中にしかない知識を見える化し、AI が使いやすいように整理する
どんなに AI が進歩したとしても、人の頭の中まで見ることはできないと思われます。
(技術的にはできても、倫理的に無理)
チームメンバーがどんなに有益な知識を持っていたとしても、それを言葉にして残さない限り、AI が活用してくれることはないのです。
詳しい人の中には、自分の知識を「これくらいは知っていて当然」と思っていたり、話すのが苦手だったりして、自分から話さない人も多くいます。
それを僕がうまく聞き出し、文書化し、AI が処理しやすい形に整理することで、その人の持つ豊富な知識をチーム資産として最大限に活用できるのではないかと考えています。
時に自分の無知を晒し、恥ずかしい思いをすることもありますが、それが今後の誰かの役に立つと信じています。
AI の活用方法を積極的に発信し、みんなが AI を活用できるようにする
AI の活用方法に関する情報はたくさんありますし、なんならそれ自体を AI に聞くこともできます。
しかし自分の周りを見た限りでは、そもそも目の前のタスクに AI を使えると思っていなかったり、上手い使い方が分からずに諦めてしまったりしている人もいます。
そういった人たちに向けて、こんな作業に AI が使えますよーという事例や、こんな指示の出し方にすると上手くいきますよーというテクニックを積極的に発信していきます。
僕1人がより高度な AI の活用方法を身に付けようとするより、まだ AI を使っていない100人が基本的な使い方を身に付けるほうが、会社全体としての利益に貢献できる気がします。
気軽に話せるエンジニアとして、常に「ごきげん」でいる
誰かに相談しなくても AI で解決できてしまうことは増えていますが、それでも時には誰かに話を聞いてもらいたいものです。
そんな時に気軽に話に行って、話した後は楽しい気分で戻って来られるようなエンジニアがいたら、チームの雰囲気も良くなるのではないでしょうか。
いつでもいくらでもというワケにはいきませんが、せめて話しかけられたときに「ごきげん」で対応できるようには心がけたいと思います。
以上、今の自分の生存戦略をまとめました。
他にも具体的なものは色々ありますが、とりあえず AI に関してはこのへんかと。
ChatGPT が本格的に使われ始めた1年前からなんとなく実践してきたことですが、今のところそれなりの評価をいただけているので、この調子で頑張ります💪
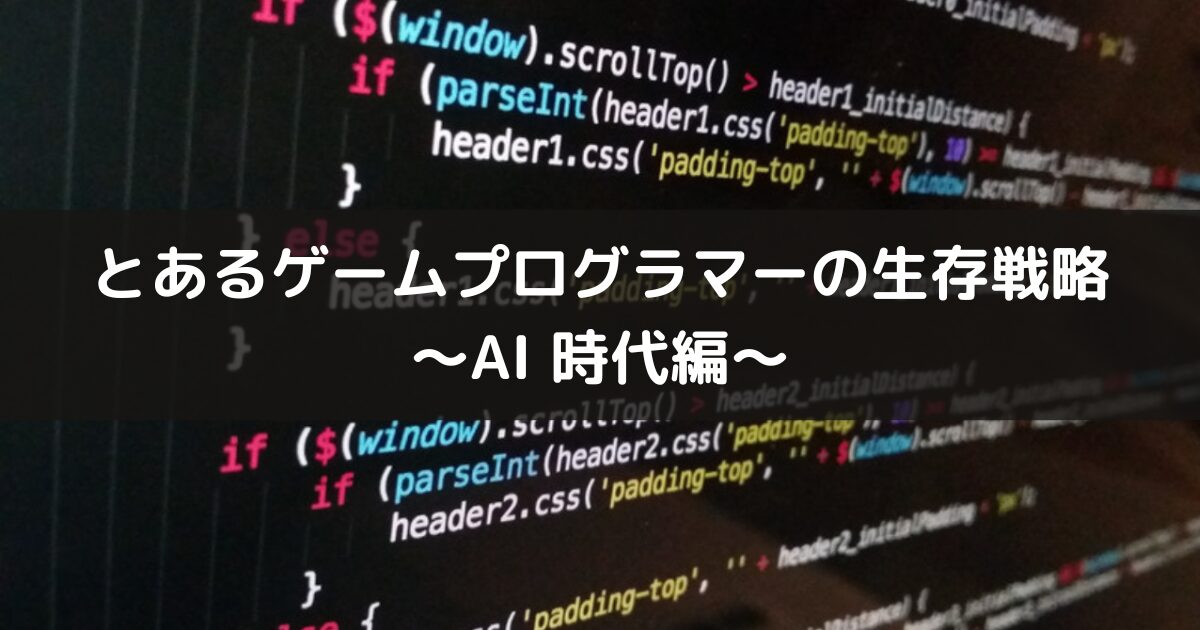

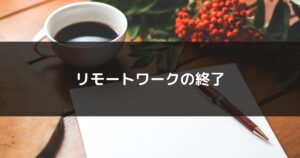
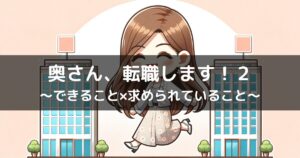
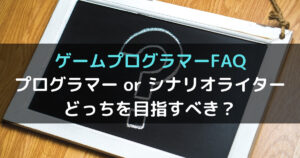
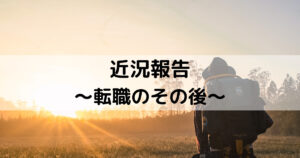
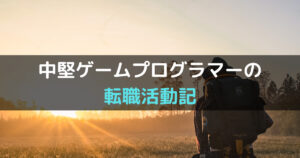
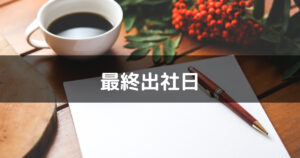

コメント