どうもです、タドスケです。
AIの登場により、これまで以上に色々なものが高速で変わっていく時代。
日々の中で「これはどうすればいいのか?」に迷うことがたくさんあります。
具体的なテクニックを探してみても、人によって全然言っていることが違くて迷ってしまったり、情報が古くなってしまっていたりします。
そんな変化の速い時代の中で、日々の行動をどのように判断すればよいのでしょうか?
僕が最近試していて有効だと感じているのは、「変わらないものをベースにする」という考えかたです
変わらないものとは?
原則
僕がプログラマーなのでプログラミングを例にします。
例えば、プログラミングの世界には多くの原則があります。
有名なものは以下です:
| 原則 | 内容 | 提唱者 | 提唱年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| DRY (Don’t Repeat Yourself) | 同じコードを重複させるべきではない | Andy Hunt, Dave Thomas | 1999年 | “The Pragmatic Programmer” |
| KISS (Keep It Simple, Stupid) | シンプルに保つべき | Kelly Johnson (航空機設計) | 1960年代 | プログラミングでは1970年代に普及 |
| YAGNI (You Aren’t Gonna Need It) | 必要になるまで機能を実装すべきではない | Ron Jeffries | 1998年 | Extreme Programming (XP) |
これらの原則が提唱されたのはいずれも何十年も前のことですが、最近の現場でも大切にされています。
「日々の仕事の学びを抽象化していくと、最終的には原則にたどり着く」ということがよくあります。
科学的根拠
原則の背景には科学的根拠があります。
例えば ↑ の原則にある KISS は、認知心理学の研究に基づいています。
人間の基本スペック
さらに科学的根拠の根幹には、「人間の基本スペックは原始時代から変わっていない」考えがあります。
有名なのは以下の本です。
旧石器時代の食事方法を真似する「パレオダイエット」も、この考えをダイエットに応用したものです。
「変わらないもの」をベースにした仕事術
科学的根拠のある方法
ツァイガルニク効果
「終わったことより、終わっていないことの方を強く意識してしまう」という性質です。
これを応用したテクニックとして、「敢えてやりかけにしておいて、無意識に考えてもらう」というものがあります。
ポモドーロ・テクニック
「ポモドーロテクニック」とは?集中力を高める時間管理術と心の整え方 – Mental Care Journal
「人間の集中力は 15~30分程度で低下し始める」という仕組みを応用し、効率の良い休憩の取り方を定めたものです。
カエルを食べてしまえ!/脳のゴールデンタイム
「人間は朝起きた直後が一番集中力が高いので、重要な仕事は朝一番に片付けるのがよい」という考えです。
個人差を加える
しかしこれらの原則も絶対ではなく、多少の個人差があります。
夜の方が仕事が捗るタイプの人もいますし、25分作業では集中し始めた頃に終わってしまうと感じる人もいます。
それでも「変わらないもの」をベースに行動してみてから、うまくいかない部分を少しだけ調整することで対応できます。
例えば僕の場合、ツァイガルニク効果をやり過ぎると「夜に頭が回り過ぎて眠れなくなり、次の日に支障が出る」というのを何度も経験しています。
この問題には「忘れてもいいようにメモを残しておく」「プログラミング作業の途中で退勤しない」という対策で一定の効果は得られています(それでもやり過ぎることもありますが…)
具体的なスケジュールに落とし込む
変わらないもの+個人差が確認できたら、それを元に実際のスケジュールを組みます。
例えば僕の場合は、以下のようにスケジュールを組みました:
- 午前中は大きい実装・バグ修正に取り組む
- 午後はミーディングやドキュメント整備を優先する
- 退勤30分前からはコーディング系タスクをせず、やりかけで退勤して過度なツァイガルニク効果が発動するのを防ぐ
- ポモドーロに収まるようにタスクを細かく区切る
もちろん計画通りにいくことはありませんが、それでも「次は何をしようか?」と毎回悩まなくて済むのは楽になります。
その他の応用アイデア
この考えは他の分野にも応用できます。
僕自身もこの考えをボイトレ・トレーニング・英語学習に当てはめて日々取り組んでいます。

情報量が多すぎて判断に迷ったときは、この考え方を参考にしていただければ幸いです!
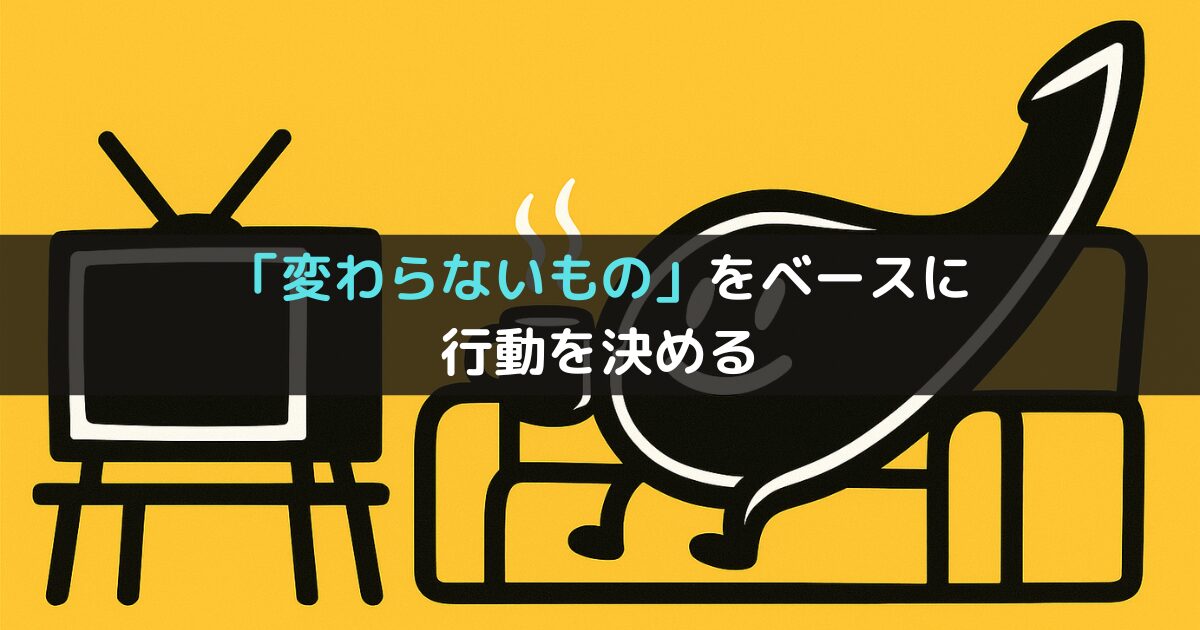



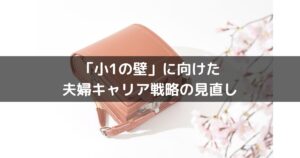




コメント